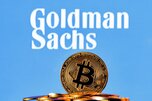日本時間4月9日午後1時すぎ、米トランプ政権は貿易赤字が大きい国や地域を対象とした新たな関税措置、いわゆる「相互関税」を発動しました。これは今月5日に導入された全輸入品への一律10%関税をさらに引き上げるもので、日本に対しては24%という高い関税率が課されることになります。
AEI (American Enterprise Institute) は、トランプ政権が設定した関税は誤った計算式に基づいていると指摘。(米国視点で)海外国が課しているとされる関税が4倍に過大評価され、結果として米国が設定する関税率も必要以上に高くなっていると述べるなか、米政権はこれに対する数字を伴う具体的な反論は行っておらず、現在も市場は混乱状態にあると言えます。
ウォール街が関税を恐れる理由
金融界、特にウォール街では関税に対して強い警戒感が示されることがあります。その背景として指摘されるのは、関税導入による保有資産価値の下落への恐れです。過去数十年にわたり、グローバリゼーションや安価な労働力の追求、債務に依存した経済成長から大きな利益を得てきた層にとっては、現状を変更する政策はリスクと見なされがちなのです。関税がこれまでの成功モデルを揺るがす可能性をはらんでいるため、金融市場の不安を誘っています。
「二つのアメリカ」と関税への期待
しかし、この見方はアメリカの一側面であり、金融センターから離れた地域に住む、いわゆる「ワーキングクラス」と呼ばれる人々からは、異なる反応が見られる模様です。彼らは長年、高騰する住宅価格、深刻なインフレ、実質賃金の伸び悩みといった経済的困難に直面してきました。そのため、関税政策が国内産業の復活や雇用創出につながるかもしれないという期待から肯定的に捉える声も聞かれます。
現代のアメリカには富裕層とワーキングクラスという「二つの異なるアメリカ」が存在するという見方があり、関税政策はこの格差に対処しようとする側面を持つとも考えられています。財務長官スコット・ベセント氏が語ったとされる「ヨーロッパで休暇を楽しむアメリカ人とフードバンクに頼るアメリカ人が共に過去最高を記録した」という現実は、この国の分断を象徴するものとしてしばしば引用され、関税が一部の人々にとって現状打破への希望となっている状況を示唆しています。
インフレ懸念への反論:データが示す複雑な現実
関税導入に対する最も一般的な懸念は、インフレを引き起こすのではないかという点です。多くの専門家が輸入品価格の上昇を通じて消費者物価が押し上げられるリスクを指摘しています。しかし、単純な「関税=インフレ」という見方に対しては異論も存在します。
例えば、2018年の中国製品への関税事例が引き合いに出されることがあります。この時、20%という高い関税率にもかかわらず、実際の価格上昇は4%程度に留まったという分析が示されました。その要因として、サプライチェーン全体でのコスト吸収や、輸出国による為替調整が挙げられています。
さらに重要な点として、関税が国内生産を刺激する可能性も指摘されます。輸入品との競争環境が変わることで国内メーカーの生産が活発化し、供給量が増えれば、長期的には価格低下圧力になり得ると考えられているのです。実際に2018年の関税導入後、一部製品価格が下落し、インフレ率も当初は低下したというデータもあり、関税とインフレの関係が一筋縄ではいかない複雑なものであることを示唆しています。
なぜ仮想通貨コミュニティは関税問題を理解しやすいのか
こうした複雑な経済状況は仮想通貨コミュニティにとっても示唆に富むものかもしれません。著名ポッドキャスト配信者のアンソニー・ポンプリアーノ氏は、通貨、貿易、分散化、国家債務といった問題に関心を持つビットコイン支持者は、関税を巡る議論の根底にあるテーマを理解しやすい素地があると指摘します。
中央集権的な金融政策や法定通貨システムに疑問を持つ人々にとって、関税が浮き彫りにする富の偏在、インフレ、通貨価値といった課題は自らが支持する分散型システムの意義を再考するきっかけとなる可能性があります。
関税政策を巡る議論は、単なる貿易問題に留まらず、国内の経済格差、インフレへの影響、そして国際関係までをも含む、非常に多層的なものです。一面的な見方を排し、様々な立場やデータに基づいた多角的な分析の重要性がこの議論から浮かび上がってきます。こうしたマクロ経済政策の動向は、新しい金融システムのあり方を模索する仮想通貨コミュニティにとっても無視できない重要なテーマと言えるでしょう。
The post 米トランプ政権、日本に24%の関税発動|インフレへの懸念は? appeared first on CRYPTO TIMES